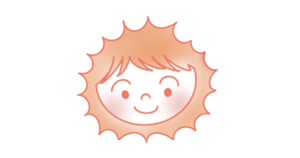成年後見制度

成年後見制度とは
成年後見制度は、判断能力が不十分な方を保護、支援するための制度です。
判断能力が不十分な方が、後見人になった人に、財産や生活などを守られ、安全に生きていくことが期待されています。
成年後見制度は、平成12年(2000年)に作られた制度で、それまでは、禁治産者という制度がありました。
禁治産者っていう言葉の響きが、よくなかったのかな。今はもうなくなりました。あなたは財産管理できない人ですよ。っていう意味が「禁治産者」という言葉に感じられます。
「成年後見」という言葉からは「後見人がついて、あなたを支えますよ。」という感じが感じられます。
制度として定着させ、判断能力は不十分になっても、財産が守られ、生活が守られるので安心して生活できるように、という制度です。
成年後見制度が、なくても家族が見守る?
家族がいれば、成年後見制度を使わなくても、何にも困らないのではないかと思ったりします。
おばあちゃん、おじいちゃんが認知症になっても、息子や娘がいれば、成年後見制度なんてなくても、財産や生活は守っていけると思ったりもします。
じゃあ、成年後見制度を利用するのは、息子や娘がいない方、身寄りがない方、だけなんでしょうか?
実際は、息子や娘が日常の生活などの支援をして、快適に生活して何も問題がなさそうな場合でも、成年後見制度がどうしても必要となってくる場合があります。
認知症になると、不動産売買や預金の管理の時に、成年後見制度が必要になります。
不動産売買の時、不動産所有者の「売買の意思」が本当にあるかどうかが、とっても問題になります。
今売るのが、一番いい、とか、ここに住んでるより、別のところに住んだほうがいい、とか、いろいろな考えありますよね。そうゆうことを判断して、自分で「不動産を売る」と決めていただかないと、不動産の売買はできません。
認知症になってしますと、すぐ忘れてしまうので、その時に「不動産を売る」と決めても、決めたことを忘れてしまって・・「本当に売るって言ったかなあ~」とか「不動産売るって言ってないよ」とかなったら、取引が進みません。ですので、判断能力がある人なのか、ちょっと怪しい人なのかの判断をする必要があります。
判断能力に問題がありそうな場合、必ず「成年後見人」がついて、その人にとってこの取引をしたほうがいいのか、よくないのかきっちり判断し、生活を守っていただけることになっています。
成年後見人には家族がなれます
成年後見人には家族がなれます。
でも、最近は身寄りのない人、兄弟姉妹が遠方であったりで、家族以外の方が申し立てをして、司法書士さんなどの専門家が、後見人になるケースも多いです。
また、家族が近くにいても、財産のことでもめていたりすると、中立な立場の方ということで、家族以外の方から後見人に選ばれるケースが多いです。
法定後見と任意後見
法定後見制度の場合、後見人は家庭裁判所が選任します。
私が認知症になったら、この人に後見人になってもらおう!!と、決めている場合は、任意後見制度を利用します。
私が認知症になったら、早い目に「任意後見制度」を考えようと思います。自分の財産をどのように使って、どのように生きていくが、全然知らない人に委ねるのって、何となく不安だからです。
でも、現実は任意後見制度はあまり利用されていません。家庭裁判所が発表している成年後見関係事件の概況をみても、任意後見は全体の2%ほど。年間700から800件です。
後見制度の利用も、認知症の増加、高齢化の増加などに比べて、そんなに多いとは思いません。申請件数は年4万件ほどです。
今後も、よりよい生活の役に立つように、制度をわかりやすく説明していきたいと思います。